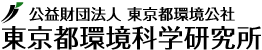自主研究
今年度の研究テーマ
| 先行的研究 |
1 | 実路走行時の窒素化合物の排出量計測及び排出量原単位の算出に関する研究 | 今後の排出ガス低減対策に資することを目的として、実路走行時のNH3、N2Oの計測に向けた測定手法の検討と、台上試験、実路走行ベースの排出量原単位の算出・比較を行います。 |
|---|---|---|---|
| 2 | 森林保全の地下水涵養に及ぼす影響に関する研究 | 都内の森林の保全により、地下水涵養量がどの程度増加するのかを評価するための基礎調査を行います。 | |
| 3 | 生物多様性に着目した化学物質による生態リスク評価手法の構築 | 農薬や重金属類を対象に、生物利用性や毒性の高い形態に着目しながら濃度実態を調査するとともに、化学物質による生態リスクが生物多様性に与える影響を定量的に解析します。 | |
| 4 | 外来付着珪藻の繁茂に影響する環境因子に関する研究 | 全国的な分布拡大が懸念される外来付着珪藻「ミズワタクチビルケイソウ」について、生育河川の栄養塩類の時空間的変動と河川の不連続性に着目し、その繁茂要因について検討します。 | |
| 5 | 送粉サービスに基づく東京都心域の都市緑地の評価手法の開発 | 東京都心域の都市緑地における生態系サービスの質向上に向けて、送粉サービスに着目した都市緑地機能の評価手法の技術的基盤を構築するために、花や送粉者における環境DNAの分析手法を開発し、送粉サービスの促進要因等を解明します。 | |
| 6 | 環境DNAを用いたアブラハヤ在来・外来系統の検出手法の開発 | 都内の河川に広く分布するアブラハヤを対象に系統特異的プライマーを設計し、環境DNAを用いたリアルタイムPCRによる在来・外来系統検出手法を開発します。また,この手法を用いて、アブラハヤの在来系統のみが残存する都内水域を探索します。 | |
| 7 | 大気中酸化エチレンの濃度変動要因の解明 | ①遠隔地における観測により越境輸送の実態を明らかにするとともに、②市販のVOCパッシブサンプラーをEO測定用に改良した連続測定システムを構築し、都内での連続観測を実施することで、EO濃度の実態とその変動要因を明らかにします。 | |
| 8 | 都市緑地に対する意識及びその多様な機能の評価-東京都23区内におけるアンケート調査の結果から- | 東京23区の都民に焦点を当て、東京都23区内の都市緑地やその多様な機能に対する都民の意識を明らかにします。 | |
| 萌芽研究 |
1 | 自然災害等による水環境への汚染を想定した無機元素の迅速分析に関する研究 | 無機元素を対象としてこれまで行ってきた平常時の河川水におけるICP-MSによる無機元素の定性(半定量)分析(迅速法)とJIS K0102-3による前処理及び定量分析(公定法)の比較データの蓄積と共に、事業場排水、平常時以外での河川水等についても迅速法による分析が有益であるかを確認します。 |
| 2 | 使用過程車からの酸化エチレンの排出量に関する研究 | 現在推計対象とされていない酸化エチレンの使用過程車からの排出量がPRTRの「大気・水域排出量」推計に与える寄与度を明らかにすることを目的とし、2024年度に確立した分析法を用いて使用過程車からの酸化エチレンの排出係数を算出し、インベントリ試算のためのデータを揃えることを目標にします。 | |
| 事業化支援研究 |
1 | 東京都市圏における生態系サービス分布の可視化推進と予測 | 緑化樹木が持つ他の生態系サービスとして暑熱緩和と生物多様性保全(鳥類)に着目し、その現状分布を可視化することで、生態系サービスを最大限活用し、負のサービスを抑える有効な緑化計画の立案に貢献します。 |
| 2 | 保全地域における緑地の評価に関する研究 | 研究所が有する緑地評価の知見を活用し、リモートセンシング技術、現地調査など、多様な手法で保全地域が提供している生態系サービスを総合的に把握します。 |
○先行的研究・・・将来的に重要性が高くなると思われるものの、研究受託に至っていない課題について、先行的に研究を行い、研究成果をもとに、委託研究や公募研究の獲得が期待できるもの
○萌芽研究・・・現在は重要性が顕在化していない環境テーマについて、独創的なアイデアにより知見の集積を行い、研究成果により、将来の研究に発展させる可能性を有するもの(研究期間:1年)
○事業化支援研究・・・公社事業の展開・充実に資する実践的研究を行い、公社における技術分野の人材育成も期待できるもの