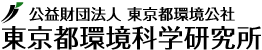評価結果 H19-1-7
平成19年度第1回外部研究評価委員会 継続研究の中間評価結果
| 研究テーマ |
有害化学物質の分析法・環境実態に関する研究
|
|---|---|
| 研究期間 | 17年度~19年度 |
| 研究目的 | 都民への健康影響が危惧される有害化学物質による、環境汚染の実態把握を行う。 |
| 研究内容 | (1)極微量でも健康リスクの高い恐れのある残留性有機化学物質POPsや、難分解性の有機フッ素化合物PFOS等の高精度・高感度分析法を確立し、都内の大気、水、底質、生物等の分析調査を行い、汚染実態を明らかにする(環境省受託調査を含む)。 (2)化学物質による環境汚染判明時に、汚染状況調査と汚染源推定などの対応を行う。 |
| 中間評価 | A3名、B2名 |
| 評価コメント及び対応 | ・人への健康リスクの高い可能性がある残留性有機化学物質について実態調査を行い、東京都においては隅田川河口においてその濃度が突出して高いこと、また東京湾底質コアにおいて有機フッ素化合物の濃度が経年的に増加していること等が明らかにされた点は、評価に値する。今後、これらの原因を特定し、その濃度を下げる処理法について検討されることを期待する。 ・ストックホルム条約の追加候補として審議が進められているPFOS等フッ素系界面活性剤を含んだPOPs関連による東京湾等の監視は重要な課題である。底質コアの分析によるこれらの年代変化などの重要な情報を提供しており、今後のさらなる成果発信が期待される。環境省のエコ調査(旧黒本調査)で2,4’-DDEが多いという特徴を持つ東京湾の生物、底質に関して、その原因探求にむけた貢献が期待される。また、類縁のフッ素系界面活性剤の中には高濃縮性の判断基準となる5,000を超えるBCF*を示す物質も含めており、より監視の幅を拡げた精力的な監視の推進、拡大を望みたい。 ・環境省の化学物質汚染実態調査の受託をベースとした研究テーマであり、注目されている有害化学物質汚染(PFOS,PFOAなど)の実態把握に貢献する有用な研究といえる。順調に進捗していると判断されるが、さらに因果関係について深めて行くことが期待される。・分析法や汚染実態の把握にとどまらず、発生源との因果関係に重点をおいた研究にシフトすることが望まれる。 ・報告を聞いた範囲や配布資料を見た範囲では、分析法の開発についてどのような検討がなされ、どのような成果が上がってきたのかがつかみきれなかったので、その点も明らかにされたい。 (事務局注)*BCF: bioconcentration factor、生物濃縮係数 ⇒有機フッ素化合物については、排出源の業種の推定に関する研究を行うこととしており、下水道局や他機関と連携しながら調査を進めていきます。また、他の物質に関しても前向きに対処していきたいと考えています。 |