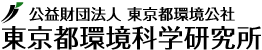評価結果 H21-2-1
平成21年度第2回外部研究評価委員会 新規研究の事前評価結果
| 研究テーマ |
生物生息環境・自然浄化機能に関する調査研究
|
|---|---|
| 研究期間 | 22年度~24年度 |
| 研究目的 | 東京湾では慢性的に赤潮が発生し、底層では貧酸素水塊と無生物域が広がるなど、深刻な状態にある。沿岸部(運河部)について、生物生息環境、自然浄化機能向上に関する調査研究を進め、東京湾の水環境改善策の検討に資する。 |
| 研究内容 |
(1)沿岸部の水質・底質・水生生物に関する調査研究 ・沿岸部での水生生物等の実態調査研究により生物生息環境の実態を把握し、生物と水環境の関係を解析する。 ・既存資料の収集、解析 (2)貝類による有害物質モニタリング ・定着性が高い貝類(ムラサキイガイ等)の生息状況を調査し、貝類に含まれる有害物質を指標として汚染状況を把握する。 |
| 事前評価 | A2名、B3名 |
| 評価コメント及び対応 | ・東京湾は人工環境がかなりの割合を占めることから、人工・都市環境と生物生息に必要な自然環境の共存を保つことが必要な水域である。本研究はこういう状況の中で、東京都として積極的な水環境保全に取り組もうとする動きをサポートするものであり、時宜を得たテーマであると同時に、重要性の高いテーマであるといえる。 ・2010年には生物多様性国家戦略が出たり、名古屋で生物多様性条約締約国会議が開かれたりすることもあり、世界的に注目が集まる状況が予想されることから、本研究のようなテーマに当研究所が取り組んでいることは、大きなアピールになるものと予想される。 ・生物生息環境の議論には、十分なデータが必要であることは言うまでもなく、本研究においても、いかにして有効なデータを効率よく収集するかという点に焦点をあてて、計画、遂行に努められることを期待したい。 ・都の生物多様性地域戦略に係わる施策への立案に向け、生物の生息環境に関する基礎情報を集積することは意義あることである。 ・可能であれば、東京湾全域について、これまでの成果(他研究機関等の成果も含め)を収集整理してみるとよい。 ・水質変化に加え、大気質の変化(例えば、日射等)の影響も場合によっては考慮することが必要になるのではないか。 ・当面の計画では対象水域が京浜運河周辺ということで、東京都に限定された形であるが、生息環境という意味では東京湾全体のデータが参考になることから、単に対象水域を今後拡大するだけでなく、他の研究機関等による同時期の東京湾内での関連調査にも目を配ることが望まれる。 ・2年目以降に具体化する自然浄化機能については、既往文献調査に既に着手しているということであるが、初年度には可能な限り幅広く文献調査をお願いしたい。 ・断片的とはいえ、これまでに多くの情報が蓄積されている問題だと思われる。研究計画立案、実施にあたり、これまでの情報を整理し、どこに焦点を当てるかを十分検討してほしい。 ・今後策定されるであろう都の生物多様性地域戦略に、どう位置付けるのかを明確にする必要がある。 ・研究結果を評価する際のバックグランドを何処にするのか、考えておく必要があろう。 ・貝類による有害物質モニタリングを計画しているが、水環境の悪化に対する位置付けがやや不明確である。 ・次年度以降、可能であれば、京浜運河以外の地域でも測定を行い,より広域での状況把握が望ましい。 ⇒東京湾全域の情報を収集して、これまでに行われた調査研究を十分活用します。大気質等の水質以外の要因影響については、気象データや当研究所内で行っている気象観測データも活用しながら把握していきます。 ⇒他の研究機関とも連携して調査研究を進めていく予定です。具体的には、国立環境研究所、千葉県、横浜市などの試験研究機関との連携を強めていきます。 ⇒文献調査については、できる限り初年度に行い、既往調査結果を踏まえて研究を進めていきます。 ⇒既往調査の内容を十分把握し、実施計画の立案を行います。調査研究の目標を絞り込み予算を効率的に執行するようにします。 ⇒研究結果を行政施策に役立つようにするため、環境局自然環境部と密に協議しながら調査研究を進めていきます。 ⇒バックグランドについては、東京湾全体の状況を見ながら設定します。 ⇒v水質悪化については、局所的に著しい水質汚濁が発生している個所を中心に調査を進め、改善策に結び付くよう展開していきます。 ⇒次年度以降は、京浜運河以外の水域も対象に調査研究を進めていきます。自然浄化機能に関しては、多様な生き物が生息できる水辺形態に関する研究にからめて小規模なエリアについての浄化機能の定量化を行っていきたいと考えています。 |