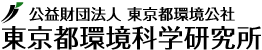評価結果 H21-2-6
平成21年度第2回外部研究評価委員会 継続研究の事前評価結果
| 研究テーマ |
有害化学物質の分析法・環境実態に関する研究
|
|---|---|
| 研究期間 | 20年度 ~22年度 |
| 研究目的 | 環境残留性、蓄積性が高く、極微量でも都民へのリスクの高いおそれのある残留性有機汚染物質(POPs)やその候補物質について分析法を確立し、環境媒体(大気及び水質・底質・生物(魚)等)中の汚染実態調査を行う。特に21年度に新規POPsとして、国際的にも規制され、環境への排出低減が予想されるPFOS等について、多摩川をはじめとする都内河川中の負荷量の変化を把握するとともに、代替物質(PFHxAやPFBS等PFOSより骨格炭素数の少なく、生体への毒性や蓄積性の低い物質)等を含めた12種類の環境実態を把握する。 |
| 研究内容 |
(1)化学物質環境実態調査 ・エコ調査(環境省受託):大気、水、底質、生物の試料採取及び分析 (2)有機フッ素化合物の水環境実態の変化に関する調査 ・多摩川など都内河川を対象としたPFOSやPFOAの規制に伴う水環境中の実態の変化の調査(代替物質等の実態調査を含む) ・地下水におけるPFOS等の濃度実態の調査 (3)リスクの高い可能性のある未規制化学物質の分析法 ・(1)のエコ調査の結果等から、都民へのリスクの高い可能性のある化学物質について、分析法の検討を実施する。 |
| 事前評価 | A1名、B4名 |
| 評価コメント及び対応 | ・国際的重要さや、全国的重要さに加え、東京都故に注意しなければならない内容、あるいは優先的に取り組まなければならない内容はないか。 ・有害化学物質問題は、世界的にみても特に重要性の高い問題とされており、本研究テーマもそれに沿ったものである。 ・特に環境省が進める環境汚染実態調査をベースとして、そこに独自設定のサブテーマを上乗せしたテーマ構成となっている点に特徴がある。 ・近年急速に注目を集めるようになったPFOS,PFOAに着目した調査は、その中でも時宜を得たものであり、都内の代表的河川である多摩川での調査は、国や他県にも有効な情報を提供することが期待される。 ・都民への有害性をもとに優先度を考える上では、人体リスクという概念を導入することがどこかで必要となってくるため、終了年度以降の研究の展開を考える際には、是非リスク評価の考え方を取り入れることを考えてほしい。 ・PFOAやPFOSについては、近年多方面で研究が行われるようになり、急速に成果が出てきはじめていることから、他の研究成果に随時目を配る必要がある。 ・化学物質の適正管理に向けて、優先順位を考えながら適切に事業を進めていると評価される。 ・新規課題とも関連するところがあると思われるが、環境省のエコ調査結果を眺めても、東京湾のPCBやDDE等の汚染状況についてはここ30年で明確な改善傾向が認めにくく、他の地域と比較しても濃度レベルが最も高く、また改善が見られにくい点が特徴となっている。どうしてこのような特徴を有するのか、新規課題との連携なども視野にいれつつ、何らかの形で取り組みを期待したい。 ・水環境における有機フッ素化合物の実態を明らかにしたことは評価できる。 ・水環境における有機フッ素化合物の発生源についても言及する必要がある。 ・有機フッ素化合物の排出規制効果について考察する必要がある。 ・最終年度にあたることから、過年度調査結果をまとめるとともに、新規研究課題への展望についても言及されたい。 ⇒都内水環境における有機フッ素化合物濃度は、他の地域と比較して、高い濃度レベルであるといえます。このため、排出源の解明や、規制による低減効果の検証を進める必要があり、いち早く取り組みます。 ⇒濃度実態の調査だけでなく、水生生物やヒトへのリスク評価が必要だとは考えていますので、これまで蓄積したデータをもとに評価を試みます。 ⇒東京湾や流入河川におけるDDT類については、過去に調査を実施しています。今後の研究テーマの一つとして、情報収集を進めたいと考えます。 ⇒これまでも排出源の調査を進めてきましたが、この成果についてさらに言及したいと思います。これに合わせて、排出規制効果については、下水処理場から多摩川への排出負荷量を算出し、検証を進めます。 |