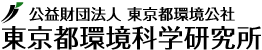評価結果 H22-2-5
平成22年度第2回外部研究評価委員会 継続研究の事前評価結果
| 研究テーマ |
微小粒子状物質等対策の効率的な推進に関する研究
|
|---|---|
| 研究期間 | 23年度~25年度 |
| 研究目的 | (1) 有機粒子の成分情報を得ることにより発生源を推定し、効率的削減対策に資する。硫酸塩の移流を観測することにより、シミュレーションモデルの推計結果を検証する。 (2) ナノ粒子の測定方法等に関する知見を収集し、環境中濃度の実態を把握する。 |
| 研究内容 |
(1) PM2.5中の有機粒子の分析方法の検討及び実測調査 分析方法:誘導体化(メチル化)加熱脱着GCMSの検討 実測調査:Ox調査と兼ねる (2) 関東地方環境対策推進本部大気環境部会 浮遊粒子状物質調査会議によるPM2.5調査:夏期 (3) 硫酸塩等の連続測定および硫黄同位体比調査 ①サルフェイトモニター、PM2.5化学成分自動測定機による観測 ②ハイボリウムエアサンプラによる浮遊粒子状物質の採取及び硫黄同位体比の測定 (4)ナノ粒子の測定方法の検討及び環境濃度の実態把握 ①ナノ粒子の測定方法の検討(サーモデニューダによる揮発成分の影響把握 ②道路沿道における濃度分布の把握 |
| 事前評価 | A2名、B3名 |
| 評価コメント及び対応 | ・国内外の複数の機関で行われている調査の成果をどのように評価をし、研究を行うのかを明確にする事が必要と考える。 ⇒他機関の調査の成果と当機関で行うことを整理していきたいと思います。 ・生成から消滅までの過程をどのように仮定し、何処の過程を調査しようとしているのかを明確にする事が必要と考える。 ⇒ご意見を参考に、研究の目的を精査していきたいと思います。 ・微小粒子状物質は、大気環境問題の中で特に注目を集めている問題であり、22年度までの3年間の成果をベースとして、さらに3年間継続して取り組もうとすることは、時宜を得たものといえる。 ・新たにナノ粒子の測定にも取り組む計画となっているが、これも緊急性の高い課題であることから、是非積極的に取り組まれたい。 ・サルフェートの同位体比は、近年かなりの知見の蓄積があると思われるので、十分な文献調査を行って、より有効な成果を上げるように努められたい。 ⇒ご指摘に従い、十分な文献調査を行っていきます。 ・幅広い分析情報を総合してPM対策にあたる研究計画が策定されている。いろいろなトピックス、分析項目を幅広く取り組み、現段階ではいささか教科書的な印象も受けるが、現場での実際の分析データを積み上げる中で共通する部分、都独自の部分などが見えてきて、他の関連研究にも波及する成果を上げられることを期待したい。 ・特に主要な発生源の自動車に取り組む課題「自動車の環境対策の評価に関する研究」を有する都の特性をうまく活かしてほしい。また、単に文献情報などを整理するだけでなく、関連する毒性研究を進めるグループとより強固な連携をとって研究を進めることも重要ではないかと思われる。 ⇒自動車については、シャシダイナモでの試験も行っており、データを有効に活用したいと思います。 ・有機粒子の成分情報からその発生源を推定し、効率的削減対策に資するという研究目的は重要であり、またユニークなものである。 ・ナノ粒子の実態把握は、健康への影響を考える上で早急に実施する必要がある。 ・野外での観測点が少ないので、増やす努力をする必要がある。 ⇒観測点については、機材人員との関係もありますが、より効率的に成果が得られる地点を精査していきたいと思います。 ・継続研究④「光化学オキシダント対策の効率的な推進に関する研究」と緊密に連携するとともに、両者の差異を明確にする必要がある。 ⇒継続研究④との連携および差異について整理していきたいと思います。 ・ナノ粒子のように新たな汚染物質についても研究を行う点は、評価できる。健康被害についても、研究を行うのが望ましいのではないか。 ・起源がわかった後、対策は具体的にどのようなものが考えられるのか。 ⇒対策は例えば人為VOC由来の粒子が多ければガソリン蒸発対策等が考えられます。 ・シミュレーションの精度の評価は、行うことは可能か。 ⇒学識経験者による検討会で議論しております。 ・ハイブリッド車、電気自動車などが普及すれば、微小粒子状物質は少なくなるのか。 ⇒自動車の寄与は少なくなっていますので、効果は普及の程度によると思われます。 |