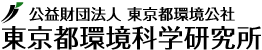評価結果 H25-2-1
平成25年度第2回外部研究評価委員会 新規研究の事前評価結果
| 研究テーマ |
微小粒子状物質の濃度低減等に関する研究
|
|---|---|
| 研究期間 | 26年度~28年度 |
| 研究目的 |
PM2.5の短期基準を超過する原因について、硝酸塩の生成条件を中心に検討し、低減対策を示すことを目的とする。また、常時監視測定結果や成分分析の充実、広域的な検討を通して、短期基準のみならず長期基準や自排局での改善を達成する方策についても示す。 ナノ粒子については、都内大気中環境濃度の実態を把握、評価するとともに、高濃度要因を明らかにする。 |
| 研究内容 |
|
| 事前評価 | A3名、B2名 |
| 評価コメント及び対応 (同様の評価及び対応は、まとめて記載) |
|