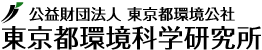評価結果 H27-2-9
平成27年度第2回外部研究評価委員会 継続研究の事前評価結果
| 研究テーマ |
微小粒子状物質の濃度低減等に関する研究
|
|---|---|
| 研究期間 | 2014(平成26)年度~2016(平成28)年度 |
| 研究目的 | PM2.5の環境基準を達成するための、低減対策を示すことを目的とする。ナノ粒子については、都内大気中環境濃度の実態を把握、評価するとともに、高濃度要因を明らかにすることを目的とする。 |
| 研究内容 |
|
| 事前評価 | A5名 |
| 評価コメント及び対応 (同様の評価及び対応は、まとめて記載) |
|