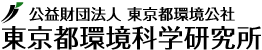評価結果 H28-1-3
平成28年度外部研究評価委員会 終了研究の事後評価結果
| 研究テーマ |
東京都におけるヒートアイランド現象等の実態に関する研究
|
|---|---|
| 研究期間 | 平成25年度~平成27年度 |
| 研究目的 | 東京ではヒートアイランド現象と地球温暖化の進行によって、過去100年の間に平均気温が約3℃上昇しており今後その影響が種々の方面に出現することが予想されている。この進行しつつあるヒートアイランド現象等の影響を確実に把握し都の施策に反映させるため、都におけるヒートアイランド現象に関する最新の現状を観測結果等により見直すことを目的とする。 |
| 研究内容 |
|
| 事後評価 | A3名、B2名、C1名 |
| 評価コメント及び対応 (同様の評価及び対応は、まとめて記載) |
|